脳梗塞や脳出血のリハビリはなるべく早く開始して寝たきりの時間を少なくすることが重要と言われています。早期より効率的なリハビリを進めるには、ご家族の協力は必要不可欠です。
寝たきりによるデメリットは?
脳卒中後は治療のため1週間ほどベット上安静となるケースが多いです。
いわゆる寝たきり状態。
この寝たきりの期間が長いと廃用症候群を呈してしまいます。
廃用症候群とは?
- 筋委縮・筋力低下
- 関節が固くなる(関節拘縮)
- 心肺機能低下・起立性低血圧
- 誤嚥性肺炎
- 認知症
- 床ずれ など
廃用症候群があるとリハビリの妨げとなります。麻痺が回復しやすい期間を無駄に過ごさないためにもなるべく早く離床することが重要です。
離床とは?
「床から離れること」ベットから起きて座ったり、車椅子に移ったりすること。
とにかく横になって寝ているだけでは何のメリットもありません。病態が落ち着いて医師の許可が下りたら可能な限り早く離床を進めていきましょう。
家族でもできるリハビリは?
「可能な限り早く離床を進めていきましょう!」
と言っても麻痺が重度で自分で起き上がれない場合は難しいと思います。その場合は看護師や介護士などの病棟スタッフに依頼して起こしてもらいましょう。
病棟スタッフが忙しくて依頼してもなかなか起こしてもらえない場合は、リハビリスタッフに起き上がりや車椅子移乗の介助方法を教えてもらいましょう。自ら介助技術を習得することで離床の頻度を増やすことができます。
ただ、少しでも介助に自信がないと感じたら必ず病棟スタッフに依頼してください。ベットから転落したり移乗時に転倒して怪我をしては元も子もないですから。
ベット上安静のときには何をしたらいい?
できることは以下の3つ。
- マッサージ
- ストレッチ
- 手足の運動
脳卒中で片麻痺になった場合、麻痺した手足はこわばり、関節は固くなりやすいです。(特に手指、肩、足首)
麻痺した手足の筋肉をマッサージしたり、足首や肩のストレッチをして麻痺側のコンディショニングを維持することができます。少しでも柔らかくこわばりがない方が運動もしやすいですから。
手足の運動は健側(麻痺していない側)も麻痺側も両方行います。特に麻痺側の運動は早期から行った方が麻痺の回復にも良い影響を与えるため推奨されています。
マッサージ・ストレッチの方法、手足の運動の内容は患者によって異なるため、担当のリハビリスタッフに聞いて教えてもらうと良いでしょう。
ベット上安静の場合、手足を下手に動かせないケースもあります。医師にストレッチや手足の運動をしても良いか必ず確認してください。
逆に、
「ベット上で寝ていれば何をしてもOK」と言われれば、ベット上で寝返りの練習をするのも良いでしょう。体幹の筋肉を鍛えたり全身運動にもなるので。
まとめです。
- 寝たきりは廃用症候群を呈し、リハビリを阻害する。
- 効率良くリハビリを進めるには早期離床。
- ベット上安静でもマッサージやストレッチ、手足の運動を行って少しでも廃用を予防する。(可能なら寝返り練習も)
何をするにも独断はいけません。
医師やリハビリスタッフに必ず確認をしてください。なかなか医師やリハスタッフに会えない場合は、看護師に尋ねてアポを取るようにしましょう。直接ベットサイドでのリハビリを見学するのも良いです。
以上、参考になれば幸いです。
でわ。


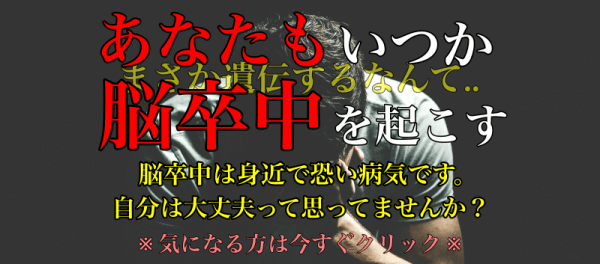



脳内出血の再生医療も進めてほしいです。期待しています。臨床試験募集があれば参加させて頂きたいです。何か情報があれば共有させて下さい。よろしくお願いします。
貞清様
コメントありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
脳出血の治験は日本では行っていません。
現在は脳梗塞が主体となっています。
また情報があれば共有させていただきます。